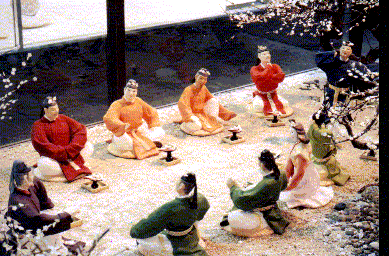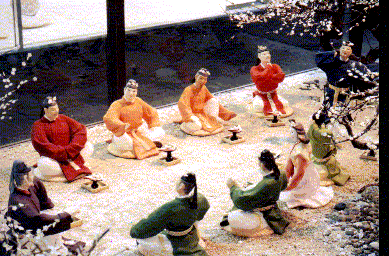筑紫万葉歌壇
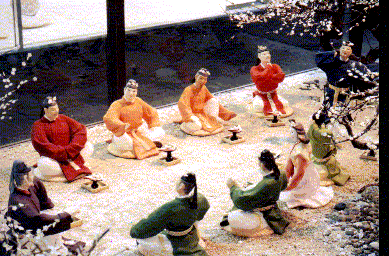
「梅花の宴」想像図
背景:博多人形師・山村延燁作
万葉集の二大歌人・大伴旅人と山上憶良が同じ時期に筑前に赴任していた。旅人は大宰府の長官の帥であり、憶良は筑前国の国司を束ねる筑前守であった。
この時期、万葉集の中心がしばらくの間、大和から大宰府に移った感さえあったのである。
<大伴旅人>
大伴旅人がはじめて大宰府を訪れたのは720年3月のことであった。
隼人の反乱討伐のため、征隼人持節大将軍という肩書きで赴任した。
それから7年後、旅人は大宰府長官(太宰帥)として着任し、730年に大納言に任ぜられて帰京するまで、約3年間の太宰府に滞在することになった。
旅人は63歳という高齢で妻の大伴郎女、愛児の家持、書持および娘、また異母妹・大伴坂上郎女などをつれて赴任している。
赴任してしばらくの間は大宰府になじみ、なごやかな日々を過ごしたようである。
しかし最愛の妻・郎女をうしなってからは、異郷の地での寂寥感にさいなまれるようになる。
孤独をまぎらすのは酒しかなく、酒をたたえる歌がめだつようになる。
同じ頃、筑前の国守・山上憶良も大宰府で妻をなくすこととなり、互いの境遇を慰めあう。
730年(天平2年)の正月13日、万葉歌人で太宰帥・大伴旅人は、宿舎で盛大な梅花の宴を催す。
歌人であった山上憶良、少弐小野老、造観世音寺別当・沙弥満誓ら文人32人がこの宴に顔をみせた。主催者である旅人の合図で、歌人達は歌作りに没頭し、梅を歌い上げる。
この時に作られた三十二首の梅花の歌が記録されている。旅人の歌は全体の8番目に掲載されている。
わが園に 梅の花散る ひさかたの
天より雲の ながれくるかも
<山上憶良>
大宰府は、「西の都」として設計され、平城京や平安京と同じように、南北の「坊」と東西の「条」が
走っていた。
高位高官の官人の宿舎は政庁の近くにあるが、官と位が下がるにつれて南へ遠ざかり、農民と入り混じって住んでいた。
山上憶良は、筑前国守としての地位にあり、いわば高級住宅街に憶良の官舎はあったはずである。
しかしそうした御殿のような大宰府政庁街から一歩外に出ると、否応なしにめにつくのが
軒を連ねた、ひしゃげた掘っ立て小屋だった。
山上憶良は、自らの境遇つまり下級官吏に甘んじた長い下積みの生活と重ねあわせながら
そうした人々の生活を見続けてきた。
国守の地位、それは憶良にとってのぞむべく最高の栄達であったかもしれない。
そのために様々な辛酸もなめてきた。
山上憶良にも大宰府での任を終え、平城京へ帰る日がやってくる。
大宰府でみた農民の姿は、都にもどっても憶良の脳裏から離れることはなかった。
彼が大宰府で見た貧しい農民達の姿は、「貧窮問答歌」の中に鮮やかに記録されている。
※太宰府周辺には、万葉の代表歌人である大伴旅人や山上憶良以外にも大伴郎女・大伴 四綱・左氏子首・沙弥満誓らの歌碑が数多く立っています。
|