貴族の衣服
何を着たのか
養老衣服令による服(資料は風俗博物館蔵より)
大宝元年(七〇一)大宝律令によって唐風をとり入れた服制が定めら
れたが、奈良に都が遷って七年後の養老二年(七一八)大宝令は改正さ
れ養老令が制定され、ここに今日に続く日本の服制の大綱が確立された。
翌三年二月には中国風の右衽(みぎまえ)の令が発せられ、古墳時代以来の左衽はこ
こで大変貌することとなる。
養老「衣服令」には、皇太子、親王、諸王、諸臣の礼服、有位者の朝
服、無位者の制服、武官である衛府の長官、次官の礼服、長官以下有位
者の朝服(軍服)、女子の礼服、朝服、制服に関する詳細な規定がある。
ほとんどの階級に共通するものは袴と履(くつ)で、それ以外は位階によって、
頭巾(ときん)、腰帯の材質、衣の色調、着用してよい布、袋の紐の色、結び方等、
厳密に定められており、一目見ただけでその人の身分が細かい所までわかるようになっていた。
しかし、その後の度々の法令に見られるように、これらのきまりはなかなか守られなかったようである。
礼服
皇太子、親王、諸王、諸臣の五位以上の者が、大祀、大嘗、元日にの
み着た衣服。中国の唐代の服制に拠ったもので、朝服に比べ新しい要素
を含んでいた。冠に玉をちりばめ、上位は織文様のある紫、緋の大抽に
簡柚の内衣を重ねて右衽とし、白の袴に深縹(こきはなだ)の紗の褶(ひらみ)を腰にまとい条帯
をしめ、綬(じゅ)や玉佩(ごくはい)をつけ、錦の襪(しとうず・くつ下)をはいた。
即位の式服には、幕末の孝明天皇まで、その間に多少の変化はあったが、この形式が用いられた。
正三位大宰帥大伴旅人はこんなスタイルで朝賀に臨んだ
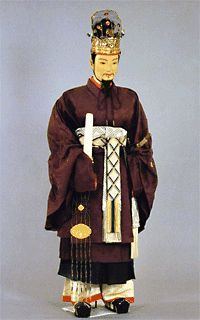
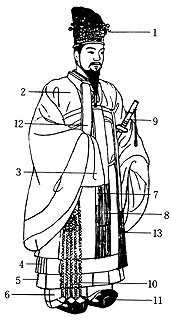 |
1 礼服の冠
2 衣(大袖)
3 内衣(小袖)
4 内衣の欄
5 紗の
6 白袴
7 條帯(綬)(長綬)
8 唐大刀の緒
9 唐大刀
10 玉
11 烏皮
12 牙笏(げしゃく)
13 綬(短綬)
|
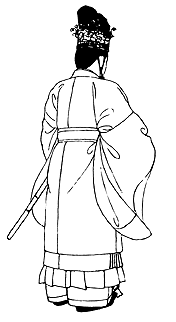 |
朝服
位のある者が日常勤務の時に着た服。一位は深紫、三位以上は浅紫、
四位は探緋、五位は浅緋、六位は深緑、七位は浅緑、八位は深縹
初位は浅縹の色の衣を着した。
白い袴、白い襪(くつ下)、鳥皮履はほば全員同じであるが、五位以
上は皀羅(くりのら)の頭巾、金銀の飾りのついた腰帯を用い、六位以下は皀縵(くりのかとり)
の頭巾に黒皮の帯を用いた。
また官人は笏を持たねばならなくなったが、五位以上は牙笏で上端を切断した形、六位以下は木笏で隅丸に作る等、五位以上と六位以下に大きな差があった。

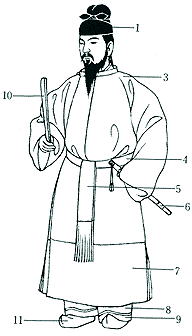 |
1 皀羅の頭巾(漆紗の冠)
2 皀羅の頭巾の燕尾
3 衣(朝服) (縫腋袍)
4 平緒
5 平緒の垂れ
6 大刀
7 衣(朝服)
(縫腋袍) の欄
8 袴(表袴)
9 大口袴
10 笏
11 鳥皮履
12 銀装の腰帯
|
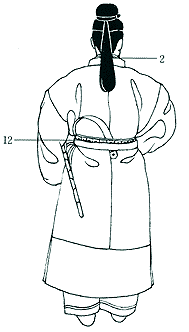 |
女子の服装
男子の制度に準じて、女子も内親王、女王、内命婦に礼服、朝服の規定、官人、五位以上の人の娘、無位の女に制服の規定が定められた。女自身位を持つ人を内命婦と呼び、夫の位階に応じる待遇をうける人を「外命婦」という。また五位以上の者の娘は父の朝服の色を除く以下の範囲でお洒落が許された。
前代との大きな違いは、上衣については男女の差がなく円領であったものが垂領になったこと。上衣の下に着ていた裳を、唐風に習って上衣の上から着けるようになったことである。朝服と礼服では髪型や衣に違いがある。
 四位の命婦の礼服
四位の命婦の礼服
旅人の妹 大伴坂上女郎は こんなスタイルで
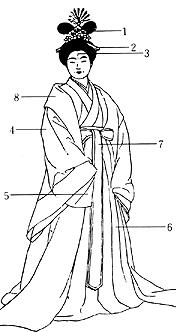 |
1宝髪
2釵子
3花鈿(眉間及び唇の両側に描かれた朱、紺等の化粧、花子ともいう)
4衣(大袖)
5内衣(小袖)
6裙
7紕帯(えそおび)
8領巾(比礼)
|
 |
奈良時代・・・庶民の衣服
材料
一般庶民の衣服は麻布製であったが、芭蕉布やパイナップル布なども
織られたことから、古くは各地において自生する植物を用いた麻布が織
られていたようである。
山上憶良の「貧窮問答歌」(「万葉集」巻五・八九二)に詠まれている様子から、当時の農民の衣服は、着用してまもなく、「わわけ さがれる」、粗い、粗末なものであったことが理解できる。自生する麻(靭皮繊維)の総てを採取し、糸を生み、布を織り、着用者の体に合わせて縫ったと考えられる。
ニ、形態
旧態のままの窄袖(つつそで)短衣系の衣服であったと考えられる。その形態は衣服令に記録されている高位高官の服飾品のうち、表面に現われない内着、中着のうち形態や機能の斬新なものが、庶民の外衣や労働者に使用された。
襦(じゅ)
庶民が着用した上衣で「冬は布襖袴・襦裙各一具」と養老令の雑令に官戸奴婢に給う衣服が記されている。
「令義解」に「短衣也」とあり、また「アハセノキヌ」と訓されていることから袷仕立の短衣であることがうかがえる。
襖子(おうし)
奈良時代には朝服・制服の内に内衣として着られたが、庶民の労働着として用いられ、筒袖の袷短衣で、短い袴とともに着用された。
半臂(はんぴ)
束帯を着装する場合、袍の下、下襲の上に着る中着のことで、袖なし又は非常に袖幅の狭い大袖で、裾に欄(横布)がついていた。
丈は袍よりかなり短く、衿は垂領仕立で、袍を着ないでこれを家着としても利用した。
衫(きん)
貴族の内衣、また庶民や奴婢は夏衣として用い、袴あるいは裙と組みあわせて着用した短衣であった。
これらはいずれも窄柚、短衣で七分丈の短袴との組合わせによって労働に適した機能性をもって広く着用された。
|